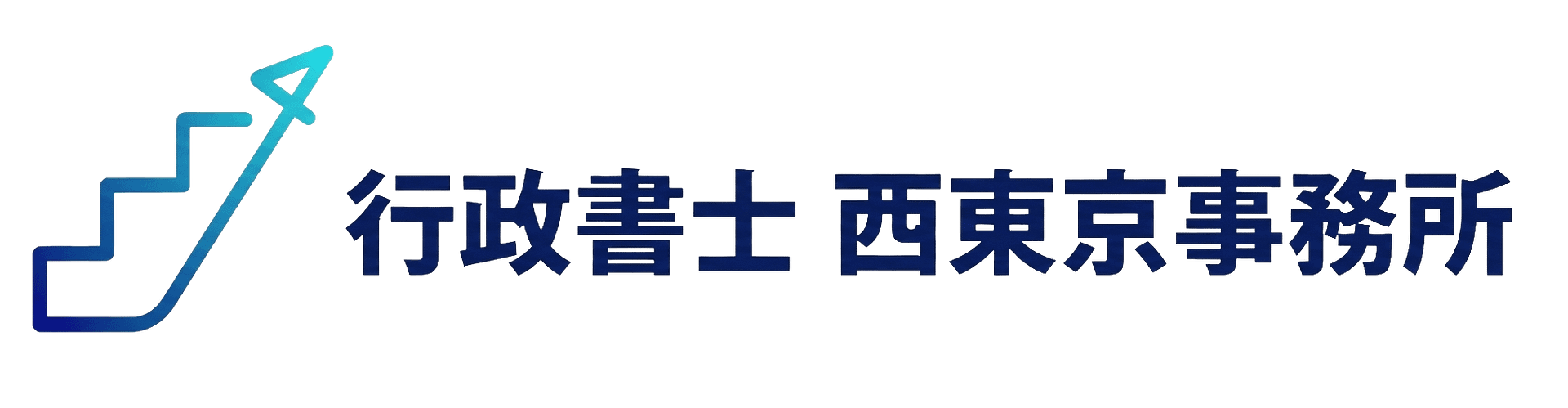判断能力が低下したり、認知症になった場合に備えるための任意後見制度について
近年、少子高齢化や高齢者の孤立化などから自身の将来的な判断能力の低下から、日常生活や医療などについて不安に感じている方が増加しています。
そのため、将来の人生設計の1つとして成年後見制度についての需要が高まってきています。
そこで、今回は成年後見制度の任意後見制度について記載していきます。
成年後見(法定後見と任意後見)制度とは
まず、成年後見制度には、法定後見と任意後見の二つに分かれており、どちらも本人の判断能力が低下した場合に本人に代わって委任した相手が財産管理や身上監護などの法律行為に関する事務をすることで、本人の保護を図ろうとする制度です。
【法定後見制度】は、本人が既に判断能力を欠く状態であり、その度合いに合わせて『補助』『保佐』『後見』の審判を開始することで、家庭裁判所からそれぞれ補助人、保佐人、成年後見人が選任され、その者が本人の代理権を付与されることで、本人の保護を行っていきます。
家庭裁判所の判断で、後見監督人が選任されることになります。
【任意後見制度】は、本人が判断能力を十分に有しているとき(補助レベル位まで)に、自身が信頼する者を任意後見人として選任することができます。
また、任意後見契約は公正証書による作成が必要であり、任意後見の開始は、本人の判断能力が低下し、医師の診断書を取得した後に、家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで任意後見が開始します。
任意後見制度のメリット
任意後見制度のメリットは、何と言っても自分が老後のことをお願いしたいと思う人に事前にお願いをすることができる点です。
法定後見では、自身が既に認知症になってから、配偶者や四親等内の親族などの申し立てにより家庭裁判所が成年後見人を選任します。
選任されるのは、家庭裁判所の成年後見人等候補者名簿に登載された者となります。
申立書には、成年後見人の候補者名を記載することはできますが、家庭裁判所が成年後見人を選任するため、必ず指定した候補者が成年後見人に選任されるとは限りません。
そのため、本人が指定した者を確実に後見人に選任するためには、任意後見契約にすることが必要です。
二つ目のメリットは、自身が認知症になった場合にどのような手続きをして欲しいかなど、事細かく打ち合わせをすることができます。
例えば、
- 自宅での生活を継続することを希望し、家事代行や公共サービスの申請について条件を決めておく
- 任意後見が開始されたら指定した高齢者施設へ入居したい
- 趣味や地域における活動(絵画、音楽、ゲートボールなど)を継続するための支援内容
- 預貯金の毎月の引き出し上限額
- SNSやオンラインサービスの取り扱いについて
- 病状が悪化した場合の治療方針や延命治療について
- 任意後見人やご家族との面会のスケジュール調整 など
事前に任意後見受任者へどのような内容にしたいのかを取り決めておくことが可能です。
三つ目に、認知症になった場合に素早く本人の意思を尊重した保護が図れることです。
事前に、任意後見契約を結んでおくことで、任意後見が開始してすぐに、任意後見人が本人の意思に沿った内容を実現します。
法定後見では、本人の利益を守るために成年後見人は、可能な限り本人に確認を行いながら調整を行っていきます。
そのため、任意後見制度の方が事前に様々な内容を詰めているため、素早い本人の保護が可能になります。
任意後見制度の利用方法
- 初回相談・ヒアリング
現在のライフスタイルや将来の心配事、支援して欲しい内容を整理します。 - 任意後見契約書の作成
本人の希望を盛り込んだ任意後見契約書を作成します。
その際、任意後見契約が開始する前に見守り契約や財産管理事務などを委任する移行型にすることが多くなっています。
また、本人が死亡した際に備えて遺言書の作成や、死後事務委任を依頼することもご検討いただきます。 - 公証役場にて契約書の締結
必要書類(本人確認書類、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書等)と実印を用意して、本人と任意後見受任者が公証役場へ出向き、契約書を作成します。 - 任意後見監督人選任の申立て
本人の判断能力が低下したときに、本人、任意後見受任者、配偶者、 四親等内の親族が任意後見監督人の選任を家庭裁判所に行います。
この選任が済むと任意後見が開始となります。
おわりに
子どものいない高齢者や、子どもが遠方にいる高齢者などは、将来、自身の判断能力が低下した場合に生活面などで不安があるかもしれません。
そのような場合に、事前に備える手段として、任意後見契約があります。
また、任意後見契約だけではなく、遺言書の作成や尊厳死宣言公正証書、死後事務委任契約などを組み合わせることで、自身の老後や死後についての希望を、認知症になった場合でも実現することが可能になります。
まずは、任意後見受任者を誰にするか?親族ではなく専門家がいいのか?など、当事務所でもご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。